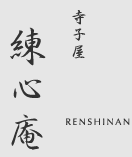2016/10/25 10月期 初歩からの宗教学講座
10月25日、三木英先生をゲスト講師にお招きしまして「初歩からの宗教学講座」を開催しました。そのときの様子を参加者の大西龍心さんがFacebookでリポートしてくだいました。
ご本人の許可を頂いてここに転載させていただきます。
皆様もどうぞ講座のご感想などお寄せください。
「生駒の山の 空高く
仰げ明星 理想の光
智徳のほまれ きそい
ただひたすらの 道をゆく」
今話題の真田丸のあった場所にある母校の校歌なのだが、生駒から遠く離れた上町大地に建つこの学校の校歌にも生駒山が出てくる。在学時代は何の疑問もなく歌っていたこの歌だが何故ここに生駒山が出てくるのか。もちろん遥かに見えるとは言え、よくよく考えてみれば少し不思議な事かもしれない。
練心庵「初歩からの宗教学講座」は宗教社会学者の三木英先生をゲストに迎えフィールドワークをふまえた宗教観とその変遷についてのお話を聞く。中でも今回は先生の調査された生駒山についてのお話が中心となり、生駒山が古来大都市に隣接した霊山であり多くの民族宗教の交錯する地である事、その力が最近衰えている事などのお話があった。
都会の人たちが何故生駒の民族宗教に惹かれるのか、それは都市世界を貫く合理主義や能率至上主義からのストレスやそれに伴う息苦しさから逃れる場として、生駒という自然環境と宗教性のある土地が選ばれたという事だが、では何故生駒が選ばれたのか。これは宗教社会学ではなく宗教学の範疇になるのかもしれないが、大阪という都市から見て生駒が四天王寺の西門から見える西方に対して朝日の登る再生の土地である事と関係するのであろうか。(これについては平城京の菅原寺で生涯を閉じた行基菩薩が遺言で「生馬(いこま)山の東陵」(奈良からみると西方)で火葬する事を願ったということもあわせて考えると面白いかもしれない)
生駒という霊山の話から霊山、聖地などに行くのは日常生活とは別のスイッチを入れる、「野生の思考」を取り戻すためという話に移り、お茶室は「都市の野生」を具現化した場所であるという話になる。ふと以前読んだイエズス教会の宣教師ジョアン・ロドリゲスの著した『日本教会史』の次の文を思い出す。
「数奇と呼ばれるこの新しい茶の湯の様式は有名で裕福な堺の都市に始まった・・・(中略)・・・たとえば場所が狭いためにやむを得ず当初のものよりは小さい形の小家を造るようになったが、それはこの都市がまったく爽やかさのない干涸びた海浜の一平原に位置しており、さらに言えば西側は荒い海岸に囲まれた砂原になっていて、周辺には泉や森の爽やかさもなく、また都の都市に見られるような数奇にふさわしい人里離れて懐旧の思いにふける場所もないからである。この都市にあるこれら狭い小家では、互いに茶に招待しあい、そうする事によってこの都市がその周辺に欠いていた爽やかな隠退の場の補いをしていた。むしろある点では、彼らはこの様式が純粋な隠退よりも勝ると考えていた。と言うのは都市そのものの中に隠退所を見出して楽しんでいたからであって、その事を彼らの言葉で「市中の山居」と言っていた。それは街辻の中に見出された隠退の閑居という意味である。」
まさにそういう点で聖地と茶室は繋がっており日常生活とは全く別の体と心の使い方をする場所であったのだろう。
1985年に刊行された『生駒の神々』と2012年に刊行された『生駒の神々』それぞれの調査から生駒において民間宗教者やその信者が減っている事に反比例して占いの店が増えてきているという報告も面白かった。これは現世至上主義が広まっている中でもパワースポット巡りやパワーストーンの流行など、これまでとは違う他界(異界)感が形成されていることを感じる。何となく感じるのは「コントロール可能な他界(異界)観」とでも言えばいいのかこちらから選んで行く事の出来るパワースポット、こちらから選んで(ご利益を)組み合わせる事の出来るパワーストーンと言う現象である。これは三木先生の指摘された「行場ではカメラに神霊が写ってしまう」という見方から「神霊を写せる」という見方に変わってきたという点とも共通するのかもしれない。
釈先生の指摘された「教団宗教者は教義を担保とし、民間宗教者は名人芸を担保とする」(担保という言葉は使われておられませんでしたがこのようなニュアンスかなと思って書きました)というご指摘は真言宗という祈祷系の宗教に属しているものとしても面白く感じた。真言宗の場合信者寺と檀家寺に大きく別れ(もちろんその中間の性格を持った寺院もある、というよりその両方の性格を持った寺院の方が多いのだが)信者寺のご住職にはこの名人芸系の人が多い。この民間宗教者の名人芸については新興宗教の問題も含めてまだまだ知りたい部分である。
とりとめのないまとめになってしまったが、次回講義に向けて疑問点をいくつか覚え書きとして書いておく
・宗教社会学、民俗学、文化人類学の守備範囲の違いはどこにあるのだろうか。
・民間宗教と民族宗教とのニュアンスの違い(三木先生は民族宗教と仰っておられたのに対し釈先生は民間宗教という言葉を使われていたように思う)
(記:大西龍心さん)